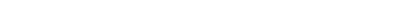書斎
体温 ── SIDE V ──
人の中に紛れれば紛れるほど、渇きはつのっていく。
血親の下から逃げ出して一週間が過ぎた。
一度は家に帰った。僕がまだ人であった頃の家に。久しぶりに帰ってきた僕を、皆優しく迎えいれてくれた。ちゃんと食事はしているかとか、ありきたりな、だが優しい質問を浴びせられ僕は悟った。
もう家に帰ってはいけなかったのだ。帰って何をするつもりだったのだろう。一緒に食卓を囲むこともできない僕。昼間はロクに動き回ることすら出来ない僕。僕は家からも逃げ出した。
人の流れに乗って街を歩き、たどり着いたのは繁華街。
昼間は建物の中で過ごし、日没と同時に外の空気を吸いに行くことの繰り返し。映画館、地下街、デパート、カラオケ、居酒屋……ここなら逃げ込む場所には事欠かなかった。特に地下街は居心地が良かった。ホームレスや酔っ払いに紛れて眠っていれば、誰からの視線も受けずに済んだ。当たり前の光景の一部になれたわけだ。
ここでなら上手くやっていけるかもしれない。
ここはまるで不夜城だ。そう、血親がいるあの根城と同じ。夜が近づくと徐々に騒がしさを増し、明け方が近づくと静けさが街を支配する。そして昼日中は普通の人々が通り過ぎるだけ。
僕も、そんな人々と何ら変わりはない。ないはずだ。ほら、現実に僕は人ごみに上手く溶け込んでいる。時折声を掛けてくる物好きがいるくらいで、誰も僕のことなど気に止めない。
──もう、誰かを食い殺すようなことはしたくなかった。
†
「いや、参ったな…まさか男だとは思わなかった」
「……そうですか?」
「だって髪長いし身体細いし」
「……そうですか」
目の前に並んだファーストフード。口にするべきかどうか僕は迷っていた。全く食べないのも不審を招くだろうが、僕は……。
その男は僕を女と勘違いして声をかけてきたらしかった。
おそらく貧弱な体格と長い髪の所為だろう。そんな経験は以前からある。男らしくない、そう言われることにも慣れている。それがコンプレックスだった時期もあったけれど、成人してからは気にしないよう心がけていた。
僕が男だと気づいて一瞬複雑な表情を浮かべた相手は、だがそのまま立ち去ることはしなかった。
寒いだろう。そんなところにいたら風邪を引くから。どこか言い分けじみた響きが感じられる台詞。男の僕を誘うことに対して自分自身を納得させているような、そんな感想を僕は覚えた。
女性を誘いたかったのならそのまま他をあたればいいのに何故だろう? まるで何かに命じられたかのように、彼は僕から離れない。
「食わねぇの?」
返答に困って僕は黙り込むしかなかった。彼は大仰に溜息をついて僕を覗き込む。
「コートも着ないで外にいたから身体冷えてるんだろ? 食えば少しは暖まるぜ?」
やはりこの状況で食べないのは不自然だろうか。僕は恐る恐る食事に手をつけた。
「もしかしてこういうの嫌いとか?」
僕の食べ方を見て不思議そうに訪ねてくる彼の心は多分善意の塊。食べられない僕に無理矢理食べさせようとしていることになど、気づく余地はないのだろう。
「嫌いというわけでは。食欲がないだけです…」
「そう? 腹減ってるように見えるけど?」
無難な返事をしたつもりの僕に対して、彼の間髪入れない冷静な指摘。
──そんなに飢えているように見えるのだろうか? 懸命に押さえ込んでいても、この渇きは隠せないのだろうか?
否。押さえられるはずだ、隠し通してみせる。
「……気のせいですよ」
それでも口調から滲み出てしまう自分に対しての嫌悪感。
「ユウってどんな字?」
僕の様子に気を使ってくれたのか、彼は話をがらりと変える。きっと優しい人なのだろう。
美味しいと感じられないハンバーガーを飲み込む。これも少しは栄養になるのか、そう考えると鬱になりそうだ。
「ユウキュウのユウです」
「ユウキュウ?」
わかりやすい例をあげたつもりだったが、彼には通じなかったらしい。少しの間の後、
「…有給休暇とかの有?」
と問い返された。あいにく僕の言ったユウキュウはその“有給”ではない。
「ユウユウジテキのユウ」
これならわかるだろうか?
「ごめん、わかんねぇや。何か書く物ない? 鉛筆でもボールペンでもいいけど。紙はこれで──」
彼が紙ナプキンを差し出してくる。行きずりの人間の名前など聞いてどうするのだろう?
「わからなくても、別に困りませんよ」
僕の答えに彼は少しむっとしたようだ。僕が馬鹿にしたように感じたのかもしれない。
口調と態度が悪かったか、それとも言葉が足りなかったのか。血親の許に居た時にも良く指摘された。もっと相手に自分の気持ちを正確に伝える術を学べと。
「漢字は記号に過ぎません。音として呼ぶことができればそれでいい。友人の名前を呼ぶときいちいち頭の中で漢字を思い浮かべますか?」
なるべく解かりやすく答えようと思いつつ、どうも回りくどい言い方になっている気がする。しかし僕にはどうにもできなかった。普段から他人と言葉を交わすことが少ないから、どう言えばいいのか解からないんだ。
「そりゃまあ確かに呼ぶ分には漢字が表示されるわけじゃないし?」
彼はがりがりと頭を掻きながらこっちを見ている。その視線にはまだ苛立ちの色。思っていることを相手に伝えるというのはどうしてこう面倒なのだろう。
「ユウ、はこう書くのかもしれない、こうかもしれない……」
テーブルの表面に指を滑らせ、いくつか“ユウ”と読める漢字を書いてみせる。
「しかしどの字を使ったとしても、貴方が口に乗せるのは『ユウ』という音に変わりはありません」
“ユウ”という音……そう自分で言ってからふと思いつく。
「……それに、もしかしたら英語の『You』かもしれませんよ」
誰にでも当てはまる単語。人波に埋没してしまいたい僕には、名前より代名詞のほうが相応しいような気がした。
†
何とか彼が僕に買い与えてくれた食事を食べきると、また外に出る。
英語のYouかもしれない、と言った僕に、彼は「どうみたって日本人だろ」と言い返してきた。
日本人。
その単語が僕の心を少し軽くする。僕はまだ他人から見ても「人」という存在でいつづけることに成功している。『君は人間だ』、そう言われたような錯覚。
礼を言った僕を、彼は怪訝そうに見つめていた。何が僕を喜ばせたのかわからなかったのだろう。久しぶりに僕は笑うことが出来たのだ。それだけでも、礼を言うには十分だった。
「コート無いってのは痛いよな。この時間じゃ店はしまってるし……寒いだろ?」
「別に」
実際寒さなどほとんど感じない。だが僕の頬に触れた彼はとても嫌そうな顔をする。
「嘘つけ。まだこんなに冷えてるじゃねぇか」
冷えているわけではない。ただ彼よりも体温が低いだけ。
「冷え性なんですよ」
「さよか」
体温が低い理由を説明するわけにはいかないので、適当に答えておく。
「で、その白衣は何? 仕事か何かで使ってるのか? いや、言いたいのはそんなことじゃなくて。それ一枚だけでも羽織ったら? ないよりマシだろ?」
彼は僕が抱えている白衣を指差す。確かに以前の僕にとって白衣は仕事着のようなものだった。今も変わらずこの姿でいるのは、少しでも今まで通りの自分に近くありたいからだろうか。
「変に注目されるから脱いだんです。街中ではもう着ません」
外出着を持って出てくるべきだったと気づいたのは家を出た随分後だった。今振り返ってみると浅はかだったと思う。
「ナンパした可愛い女の子相手なら、俺だって格好つけてコートの一枚くらい貸すけどよ。野郎相手には貸さねぇぜ?」
「貸してくれなんて言っていませんって」
「それは何かい? コートの要らない暖かい場所に連れて行けってこと? ユウが女だったら──」
彼の台詞が途切れる。
「僕が女だったら?」
「……あぁ、ユウが女だったら俺の奢りで徹カラぐらい連れて行ってやろうかってとこだな。んで、朝まで歌いながら寒さしのぐ」
「……僕は寒くないですよ」
僕はそう繰り返すしかなかった。それが真実だから。
彼は唐突にマフラーを外し、僕の首に巻きつけた。今まで隠れていた首筋が露わになり僕の視界を占領する。
「可愛い女の子じゃねぇから、マフラーで我慢しな。ほれ、手袋も貸してやるよ。……?」
彼の声が聞こえるが何を言っているのかわからない。ただ、首筋が目から離れない。
「何だよ?」
頚動脈はココ──
「うわ冷てっ!」
彼の悲鳴に我にかえる。僕は何をしていたんだろう? 何を考えていたんだろう?
僕は彼に何をしようとしていた……?
「……ごめんなさい」
自分は決めたのではなかったのか、もう誰も手にかけないと。
心の底から謝った僕の言葉は、彼にとっては意味不明に違いない。
「……寒いでしょう……?」
取り繕うようにそう続けた。
彼はにこにこと人のいい笑みを浮かべている。
「そっちほどじゃないさ。このぐらい平気だって」
「貴方が平気でも僕が平気じゃないんです……」
視線を落とし、じっとアスファルトを見つめる。彼を見れなかった。顔を上げればまた彼の首筋を見てしまうだろう。
「そんな気にするなよ。何だかこっちが悪いことしてるみたいじゃねぇか」
苦しい程の飢えと渇き。どうにもならない欲求が湧き上がる。網膜に焼き付いて離れない、皮膚から透けて見えた彼の頚動脈の色。
「ユウ?」
身動きが取れない。気持ちが悪い。これは渇きの所為せいではない。さっき食べた食事がいけないんだ。そうに違いない。僕は渇いてなどいない。
「おい、ユウってば!」
彼の声が頭に響く。頭がグラグラする。
「どうかした?」
何時の間にかしゃがみこんでいた僕を彼が気遣うように覗き込んでくる。彼の首を見ないように、目だけを見るように僕は懸命に顔をあげた。
大丈夫だと答えようとしているのに声が出ない。
「何? 聞こえないって」
「……ぃ……」
苦しい。
自分の喉に爪を立てて引っ掻く。いっそこの喉が無ければ──!
「何やってんだよ!? どうしたんだ!?」
彼の手が僕の腕を掴んだ。熱い掌。血の流れが感じられるような掌。
「……気持ち……悪い」
「へ?」
「苦し……」
渇きが全身を苛んでいく。思考すらその渇きに飲み込まれそうだ。
「……か……て……」
喉が渇いて仕方が無い。違う、渇いていない。渇いていない。渇いていない。渇いて――
僕を抱きとめた彼の鼓動が聞こえる。
「とりあえず救急車……」
僕に残された最後の理性が警鐘を鳴らす。
そんなもの呼ばれるわけには行かなかった。病院に連れて行かれてしまったら、僕が異形の存在であることが暴かれてしまう。それは重大な掟違反だ。
このままでは彼を消さなければいけなくなってしまう。我々の存在を危うくするものは全て始末されなければならないのだから。食い殺すどころの話ではない。糧になるわけでもなく、ただ殺さなくてはいけなくなってしまう。
僕は必死に彼の腕を掴んだ。
「いらな…い…呼ばな……いで……」
絶対に呼ぶな、との思いを込めて彼を見つめる。
「少し我慢してくれよ」
携帯電話をしまうと彼は僕を軽々と抱き上げた。
彼の腕の中で僕は自分の中の獣をを抑えこむことだけで精一杯だった。
「っとに大丈夫かよ…?」
取り込むことの出来ない異物を、機能しているのか怪しい胃が押し戻す。ホテルのバスルーム。彼は本気で僕を心配して、ずっと背中をさすっていてくれた。
「まだ気持ち悪い?」
食べさせた自分が悪いとばかりに、彼はひたすら謝り続ける。
胃の中が空っぽになって、やっと僕は立ち上がる。これでもう調子は元に戻るはずなのに、眩暈は治まらず視界が揺らぐ。
「馬鹿! 調子悪いやつは大人しくするんだよ!」
彼は有無を言わさずふらつく僕を担いだ。触れ合った部分から彼の体温が伝わってくる。おかしくなりそうだ。
ベッドに下ろされ、布団を掛けられる。僕の姿は彼の目には病人として映っているのだろう。
「あ……」
彼を見ないよう、彼の首筋を見ないよう、視線を天井に走らせる。
「安心しろ、襲ったりしねぇから。ゆっくり休めよ」
そう告げると彼はベッドの縁に腰を下ろした。
その声に混じって違う音が聞こえた。異様なまでに鋭敏になった感覚が、テレビのノイズのような音をとらえている。テレビなどついていないのに?
赤ん坊はテレビのノイズを聞くと落ち着くという話をしてくれたのは誰だったか。テレビのノイズは母親の身体を流れる血液の音に似ているから、赤ん坊は胎内にいた自分を思い出して心安らぐと。
今ならわかる気がする。なんて綺麗な音なんだろう。
血の流れる音。
彼の血の流れる音。
「ユウ……?」
腕の中に彼の体温を感じる。胸に回した掌には鼓動が直に伝わってくる。
「おいおい、何の冗談だよ? 女だったら大歓迎だけど……」
頚動脈の位置はココ。
「──!?」
腕の中で彼がもがく。
振り返った彼の瞳に映った僕の瞳は、血のように真っ赤な色をしていた。
──もう、誰かを食い殺すようなことはしたくなかった。
彼一人ではこの渇きを満たすには足りない……